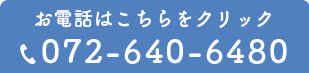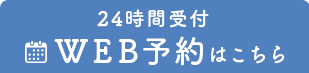「噛み合わせ」と聞くと、歯並びや食事のしやすさを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実は、噛み合わせは全身の健康にも深く関係しています。
今回は、見えないけれど重要な存在である「噛み合わせ」が、身体に与える影響について詳しくご紹介します。
「噛み合わせ」とは、上下の歯が接触した時の歯の位置関係や動きのことです。
噛み合わせは、食べ物の効率よい咀嚼だけでなく、顎の関節、筋肉、さらには姿勢やバランス感覚にまで影響を与えます。
噛み合わせの乱れがもたらすトラブルには、以下のようなものがあります。
【1】顎関節症
噛み合わせが悪いと、顎関節に過度な負担がかかり、顎の痛みや開閉時のカクカクという音、口が開きにくいといった症状が現れます。
これがいわゆる「顎関節症」です。
【2】頭痛・肩こり・腰痛
嚙み合わせのバランスのことを、「咬合バランス」といいます。
咬合バランスの崩れは、咀嚼筋の緊張を引き起こし、それが首や肩の筋肉に波及して、慢性的な肩こりや頭痛、腰痛を誘発することがあります。
【3】姿勢の乱れ
噛み合わせは、実は身体全体のバランスに関係しています。
左右どちらかの歯でばかり噛んでいると、筋肉の発達に差が生じ、顔の歪みや姿勢の乱れを引き起こすこともあります。
【4】集中力や睡眠の質の低下
噛み合わせによって引き起こされる筋緊張は、自律神経にも影響します。
そのため、眠りが浅くなったり、集中力が続かなくなったりすることもあるのです。
先程少し触れましたが、私たちは無意識のうちに、自分なりの「噛み方」をしています。
「右側ばかりで噛む」「奥歯だけを使う」「前歯をほとんど使わない」など、日常の「噛み癖」が、実は噛み合わせの乱れや体調不良の原因になっていることがあります。
よくある噛み癖には、次のようなものがあります。
【1】片側噛み
利き手があるように、嚙み方にも「右側ばかり」などの癖があります。
しかし、いつも同じ側でばかり噛んでいると、左右の筋肉や歯の摩耗に差が出て、顎のズレや歯列のゆがみに発展することもあります。
【2】噛みしめ・食いしばり
緊張したとき、無意識に歯を食いしばっていませんか?
これも一種の噛み癖です。
歯に過剰な力がかかると、歯の破折や知覚過敏、顎関節への負担が生じます。
【3】前歯を使わない
前歯は見た目だけでなく、食べ物を噛み切るという大事な役割を担っています。
前歯を避けて奥歯ばかり使っていると、前歯が次第に機能を失い、噛み合わせのバランスが崩れることもあります。
【4】唇や頬を噛む
これも立派な噛み癖です。
ストレスや不正咬合が原因で起こることが多く、粘膜を傷つけたり、炎症を繰り返したりする恐れがあります。
もしこのような症状があれば、歯科医院で相談してみるのがよいでしょう。
噛み合わせの問題は、歩き方の癖などと同様、中々自分では気づきにくいものです。
もし以下のような症状があれば、一度歯科医院で検査をしてもらった方が良いかもしれません。
・顎が疲れやすい、痛む
・口を開けると音がする
・食事中に歯が当たりにくい
・顔の左右差が気になる
・慢性的な肩こりや頭痛がある
治療方法には、マウスピースによる咬合の調整、矯正治療、被せ物や詰め物の調整などがあります。
適切な治療は人によって異なります。歯科医院で先生と相談してみましょう。
「たかが噛み合わせ」と思われがちですが、身体の不調の原因が実はそこに隠れていることも珍しくありません。
毎日の生活をもっと快適に、もっと健康にするために、「自分の嚙み方にはどんな癖があるかな?」と考えてみると良いかもしれません。
茨木市彩都で土曜日・日曜日も診療する歯医者
彩都西歯科クリニック
大阪モノレール 彩都西駅から徒歩3分 駐車場完備